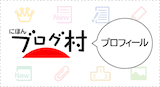NHKで毎週金曜日に放送されている『チコちゃんに叱られる!』で紹介された雑学や情報を紹介しています。
5才のチコちゃんが問いかける素朴な疑問の数々。
答えられないと、チコちゃんに「ボーっと生きてんじゃねーよ!」と叱られてしまいますよ。
まだ知らない疑問や不思議がたくさん登場します。
一緒に楽しみながら知識を深めましょう!
今回は、7月25日(金)の放送分で紹介された雑学です。
人を呼ぶときに使う【君】ってなあに?
ふだん当たり前に使っている「〇〇君」。
なぜそのような言葉を使うようになったのでしょうか?
吉田松陰が立場を超えてコミュニケーションをとれるようにしたことば

解説
「君」その由来とは
吉田松陰は江戸時代後期の教育者で、長州藩(現在の山口県)で松下村塾を開いた人物です。
現在も山口県萩市には、当時の「松下村塾」が遺されています。
松陰はここで高杉晋作や久坂玄瑞、明治時代に総理大臣となった伊藤博文や山県有朋などを育てました。
松陰は月謝をとらなかったことで、様々な家柄や立場の若者が通うことができ、多くの偉人を輩出したと言われています。
因みに高杉晋作は武家、久坂玄瑞は医者家庭、伊藤博文は農家の出身でした。
また、松陰の教育方針にも特徴があります。
教科書などがない中で松陰の講義を聞かせたり、「生徒同士の討論」を大切にした、自由な教育を実践していたと言います。
「立場の差」「年齢の差」「進み具合の差」の壁を超えて生徒同士に討論させることにより、生徒たちの個性を伸ばしたというわけです。
しかし、当時は生徒それぞれに身分の差があり、それが対等な討論を難しくしていることに松陰は頭を悩ませます。
家柄や立場の違いがあると、意見が言いにくい。
そこで松陰はあるとき生徒たちに提案します。
「身分が上の者には様、下の者には殿、それでは対等な意見など言えません。」
「お互いの呼び名に “君” と付けてはどうでしょうか。」
「家柄は変えられなくても、呼び方なら変えられます。」
こうして松陰は松下村塾では、本来立場の高い人につけた「君」をお互いに使うことにより、対等な立場と相手への尊敬の気持ちを込めたのです。
その後の拡がり
その後、明治時代になると武士などの階級も取り払われ、全国に学校が作られました。
この頃から「対等で親密な仲間意識」を表す新しい時代の言葉として「〇〇君」という呼び方が浸透し、教科書にもその呼び方が載ったことから、全国の小学生たちにも広がていったと考えられています。
国会では今でも議員を「〇〇君」と呼びますが、参議院先例禄に「互いに敬称として “君” を用いる。」と記されているためです。
明治23年に日本で初めて帝国議会が開かれたときから、議長は発言者を「君」付けで呼んでいました。
その第1回帝国議会で初代内閣総理大臣を務めたのが、松陰の教え子である伊藤博文だったのです。
まとめ
自分を「僕(ぼく)」、相手を「君(きみ)」と呼ぶことを定着させたのも、吉田松陰だと言われています。
かつては学校で男子は「君」、女子は「さん」付けで呼ばれていましたが、多様性が広がる時代の流れとともに、現在では全員「さん」付けで呼ぶことがほとんどです。